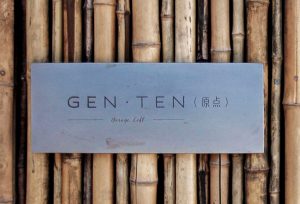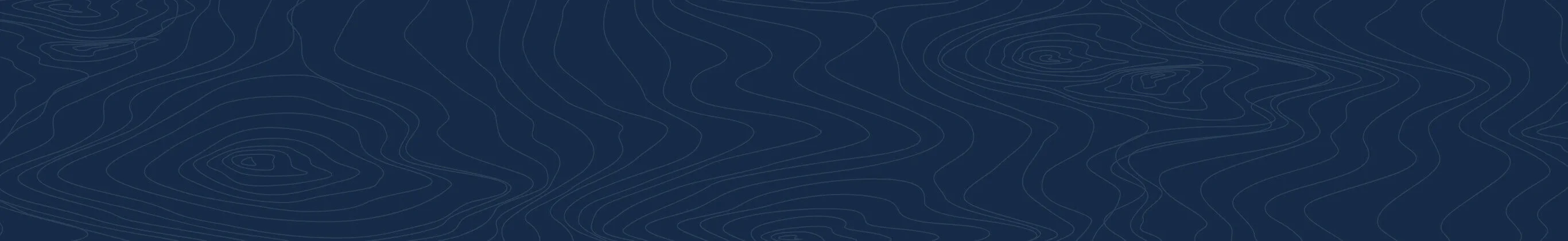-
カテゴリから探す
カテゴリを選択してください
-
タグから探す
タグを選択してください

はじめに
近年、古民家を再生して、レストランやカフェ、雑貨屋さん、宿泊施設などとして活用する「古民家再生」の試みが増えてきています。今回はその中でも、古民家を再生して宿泊施設として活用する取り組みにつての、メリット・デメリットと、実際に私が訪れた宿泊施設の一部を紹介していこうと思います。
日本の空き家問題の現状
今後、少子高齢化の更なる加速により空き家問題は深刻化していくと予想され、管理が放棄され、防災、防犯、衛生、景観など様々な面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空き家も増加していくと考えられています。
全国には約850万軒の空き家があり、総住宅数に占める空き家の割合は約13.5%にも及びます。この数は8軒に1軒が空き家という状況を表しています。
そんな中、日本特有の建築技術や日本人の生活習慣が息づいており、地域の歴史や気候も感じ取ることのできる文化的価値の高い建築物である古民家も、空き家化が進み、多くの古民家が解体されてしまっています。
古民家の解体が進むと、結果的に日本の貴重な文化が失われ、地域の魅力を低下させることにつながり、地域の産業衰退も招いてしまうのです。
分散型ホテルという取り組み
旅館業法の改正
2018年6月15日に旅館業法が改正されました。
これまでの、旅館業には、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の4種類がありましたが、今回の旅館業法の改正により、これまで異なる種別であった、「ホテル営業」と「旅館営業」が統合され、「旅館・ホテル営業」となり旅館とホテルの種別が一つになりました。
旅館業法が統合された後の「旅館・ホテル営業」では、ホテルでは最低10室、旅館では最低5室の客室が必要だったところ、最低客室数の基準が撤廃され1室から営業が可能となりました。
さらに、ホテルは洋室でベッド、旅館は和室で布団という規制や、客室の最低床面積の規制など、構造設備等の規制が緩和されたほか、緊急時の駆け付けの態勢、ビデオカメラによる本人確認などを条件に、玄関帳場・フロントを設置しないことも認められるようになりました。
分散型ホテルの誕生
今回、旅館業法の改正により、様々な規制が緩和されたことで、一棟一棟が許可の要件を満たしていれば、建物が一つではなく、まちに分散していても一つのホテルとして営業することが可能となり、新たな形態の宿泊施設である「分散型ホテル」が誕生しました。
分散型ホテルとは、イタリア発祥の、空き家を活用して「まち全体をホテル」と見立てたもののことをいいます。
一般的なホテルでは一棟にまとめられている、フロントやバー、レストラン、客室などの機能が、分散型ホテルでは、一棟にまとまっておらず、フロント機能を備えた場所、レストラン、バーなど食事をする場所、宿泊する場所などが、まちに点在しています。
空き家や歴史的建造物などをリノベーションして宿泊する場所にし、食事や買い物、入浴は地域のお店を利用してもらうケースが多くみられます。
そのため、地元住民が普段利用するお店を訪ね、地元住民との交流が楽しめるなど、まるでそのまちに暮らしているかのような体験ができると、注目を集めています。
分散型ホテルのメリット・デメリット
分散型ホテルのメリット
- 宿泊客が地域のお店を利用して地域経済が循環する
- 空き家の解消、町並みの保全
- 観光、雇用の創出
分散型ホテルのメリットは、宿泊客をひとつの建物に囲い込まないことです。
自分のホテルで宿泊客を囲い込み巨大化していくと、囲い込みの過程で、観光客はどんどん地域のお店を利用しなくなっていき、まちは衰退していくという事態に陥ってしまいます。
一方で分散型ホテルでは、フロントでチェックインを済ませた宿泊客は、地域を散策しながら宿泊する場所へ移動をします。チェックインの際に、地域のマップと地域のお店で使えるチケット等を配るケースも多くあり、地域のお店の利用を促すことで、地域の飲食店や土産物屋など、まち全体が収益を得られる仕組みになっています。
分散型ホテルと、地域のお店や地域住民が一体となって宿泊客をもてなすことで、宿泊客に、より地域の魅力を感じてもらうことができます。
また、分散型ホテルと地域住民が密に連携することで、地域への新たな観光や雇用の創出につながります。このように、分散型ホテルは空き家解消のみならず、地域活性化に期待ができるのです。
分散型ホテルのデメリット
分散型ホテルはチェックインを済ませたら、まちに点在した宿泊場所へ移動します。
一箇所だけですべてが完結しないため、移動が必要となり、面倒だと感じる場合があるかもしれません。
しかし、移動の中で、地域住民と交流したり、地域住民しか知らないようなディープなスポットへ訪れたりして、地域に溶け込み、地域のリアルな生活を体験することができるので、移動も楽しむことができます。
分散型ホテルの紹介
ここでは、実際に私が訪れた分散型ホテルの紹介をしていこうと思います。
佐原商家町ホテルNIPPONIA
佐原商家町ホテルNIPPONIAのある佐原の町は、小野川沿いの水郷商都が重伝建地区に選定され、江戸時代から続く佐原の大祭はユネスコ世界無形文化遺産に登録されています。
佐原商家町ホテルNIPPONIAでは、築100年超の古民家や蔵を含む建物を宿泊施設、飲食店などに改修して、歴史的なまち並み全体を、ひとつのホテルと見立てています。

香取街道と小野川の交わる町の中心地に位置し、フロントとレストランの役割を担う棟、“GEISHO”は、県の有形文化財であり、荒物や雑貨を扱う商家だった建物で、佐原のランドマーク的存在となっています。

歴史ある客室での滞在や、千葉の味覚を愉しむ本格フレンチ、近隣の銘店や店舗と連携した街歩きなど、佐原の文化、歴史、食、暮らしに溶け込むように泊まる新しいスタイルの宿泊体験をすることができます。
商店街HOTEL講 大津百街

滋賀県の大津はかつて、「大津百町」と呼ばれるほど賑わっていた、東海道五十三次最大の宿場町です。
かつての宿場町の商店街にある、築100年以上の町家をリノベーションし、「街に泊まって、食べて、飲んで、買って」をコンセプトにしています。
「商店街HOTEL 講 大津百町」では、宿泊税や入湯税と同じように宿泊者一人から150円を宿泊料金に内包し、その総額を商店街に寄付して活性化に役立てています。
このような、宿泊することで街が活性化する仕組みを「ステイ・ファンディング」と名付けています。宿泊客は、繰り返し宿泊することで、自らがまちの活性化に貢献できるのです。

宿泊棟は大津の中心部であり、庶民的な活気に包まれたアーケード商店街の中に点在しています。
商店街HOTEL講 大津百街では、商店街ツアーも開催しており、普段観光客は立ち寄らないような地域のお店に訪れ、地域住民と交流することで、地域に根差したリアルな生活を体験することができます。
まとめ
分散型ホテルのメリット・デメリット、実際に私が訪れた分散型ホテルの紹介をしてきましたが、分散型ホテルに少しでも興味を持っていただけたでしょうか。
古民家の再生は一棟一棟で完結してしまうのではなく、古民家を地域の大切な資源として、地域全体で古民家を再生していくことがとても大切になってきます。
分散型ホテルは、地域住民と一緒に宿泊客をもてなす宿泊施設であり、地域の文化や魅力を発信することができます。
そうすることで、観光客や宿泊客が増加し、地域に経済的な効果や、空き家問題の解決など、地域に貢献できる取り組みなのです。
私たち都田建設のあるドロフィーズキャンパスも、地域の方々が使わなくなった建物や敷地をお借りして、カフェやインテリアショップなどの、北欧のスローライフやオーガニックな生活を感じる事ができる施設へと生まれ変わらせています。
そんな都田の地域に溶け込みながら、北欧のスローライフを体験できるドロフィーズキャンパスへも是非遊びに来てください。
鈴木将太 / 家づくりアドバイザー
人気記事
POPULAR
おすすめカテゴリー
RECOMMEND